島村英紀が撮ったシリーズ 「不器量な乗り物たち」その4:日本編
「不器量な乗り物たち」その1:生活圏編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その2:極地編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その3:深海編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その5:鉄道・路面電車編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その6:戦前・戦中編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その7:その他編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その8:その他編の2はこちらへ
![]()
島村英紀が撮ったシリーズ 「不器量な乗り物たち」その4:日本編
「不器量な乗り物たち」その1:生活圏編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その2:極地編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その3:深海編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その5:鉄道・路面電車編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その6:戦前・戦中編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その7:その他編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その8:その他編の2はこちらへ
![]()
1-1:敗戦国日本の「庶民のための車」その1・フジキャビン5A型 (1955年)
第二次世界大戦の敗戦国として焦土から立ち上がった日本とドイツは、1950年代には経済成長を遂げ、戦争の傷跡も消えかけていた。
ファミリーカーは、当時の人々にとって、とうてい手の届かないものだった。このため、メーカーとしては、少しでも安く、少しでも簡素に作った質素な車を一生懸命作り上げた。これは日本に限らず、ドイツも、また戦勝国ではあってもやはり焦土から立ち上がったフランスでも同じだった。
車である以上、1人乗りというわけにはいかない。しかし4人乗りだと大きくて高くなってしまう。こうして2人乗りになった。
ヘッドライトは、1つのほうが、もちろん2つよりも安い。タイヤは4つよりも3つのほうが安い。そのうえ、後輪を1つにすることによって、ディファレンシャル・ギヤのような複雑で高価なメカニズムが不要になる。
こうして、あちこちを切りつめていって、この左の写真のフジキャビンが出来た。
方向指示器も、これならばたったいひとつで、前からも後ろからも見える。
設計したのは富谷龍一氏である。なお、氏は下の2-1のフライングフェザーも設計した。日本では有数のすぐれた設計者だと思う。初期のシトロエン(フランス)の名車を作ったフラミニオ・ベルトーニにも匹敵するかもしれない。車を作ったのは、日産自動車系のエンジンメーカーだった富士自動車であった。オートバイも作っていた。いまはなくなってしまったメーカーである。
つまり当時は、フランスも日本も、一人のすぐれた設計者が存分に腕を振るえる時代だったのだ。オースチン・ミニを作ったアレック・イシゴニスもその一人だ。 近年のように、マーケットリサーチだ、コンサルタントだ、重役の承認だ、といった数々の障壁ゆえに、時代を超えた特徴のある車が出せなくなったばかりか、どの車も横並びで面白くなくなってしまった時代からは考えられない、良き時代なのであった。長年の「スバル党」である私が近年のスバル車に、以前ほどの魅力を感じなくなってしまったのも、同じ理由からである。
小型車には小型車のデザインがある。しかし、大型乗用車にあこがれて、ちまちまとした物真似になってしまった哀しい姿の車、たとえば、ドイツのロイト600や日本の二代目トヨタ・パブリカと比べれば、このフジキャビンのデザインは、なかなかユニークで優秀だ。
左上の写真に見られるように外装はプラスチック(FRP樹脂)で、軽くて、安く作れる。この車の重さはわずか145kgしかない。モノコックボディという、軽くて強いボディ形式を採った。当時としては先進的な構造で、日本の乗用車がモノコック構造を普通に採用し始めたのは1960年代だった。
この車の尻尾は、なんとも愛らしい(右の写真)。エンジンを中に入れ、その熱気を抜くためのルーバーを3つ切り、そしてエンジンを点検したり修理したりするためのフード(蓋)を、蝶番で両側に着けただけの必要最小限の装備だが、巧まざる愛嬌になっている。フードは蝶の羽のように両側に開く。
初期モデルでは、運転席のドアは左側にしかなかった。モノコックボディの強度を確保するためだったろう。しかし、あまりに不便だったので、後のモデルではこの写真のように左右1枚ずつのドアになった。
なお、いちばん上のルーバーの左側はガソリンを補給するための燃料注入口である。エンジンの上にガソリンタンクがあり、そこに発火性が強いガソリンを補給するのは危険なことだったが、それはほぼ同時期に作られた「僚友」、ドイツのハインケルでも同じだった。
じつは富谷氏はドイツの小型車を研究していた節がある。前2輪、後1輪という構成といい、後部にエンジンをおくことといい、ドイツから学んだのであろうか。
ハインケルの後部も可愛らしい。しかし、ちゃちなものとはいえ、バンパーが前部と後部に着いているのは、ドイツのほうが、少しは衝突安全性を考えていた、ということであろう。
エンジンは2サイクルエンジンで、空冷単気筒。121ccで、わずか6.5馬力(125ccで4.75馬力という説もある)だった。

ところで、この車のハンドルは、左の写真に見られるように、世界でもユニークな形をしている。似ているのは、ドイツのメッサーシュミットくらいのものだ。
たしかに、考えてみれば、ハンドルが丸い必要はなく、近年ではやや楕円型のハンドルも出てきたが、これほど極端な楕円のハンドルは珍しい。
馴れるのに時間がかかりそうだが、他方、走り出すときに、前輪がどちらを向いているか直感的に分かる、という利点もある。
また、1本スポークという意味では、フランスの初期のシトロエンとも似ている。
メーターは一つしかない。速度計だけだ。公称最高速度は60km/hだった。速度計と対象的に左側にあるのは、イグニションスイッチ(鍵穴)である。ハンドルの中央部に滑稽な形で運転者に向かって突きだしているのは、ライトのスイッチと、方向指示器のスイッチだろう。
この車の全長は295cm、幅は127cmである。かろうじて2人が横並びで座れる幅だ。
この車は1955年に発表され、23万5千円で翌1956年に発売されたが、わずか85台しか作られずに1957年に生産を終えてしまった。日本人は、こんな質素な車でさえ、まだ買えるだけの収入や余裕がなかったのであった。
(2005年に、愛知県愛知郡長久手町のトヨタ自動車博物館で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは44mm相当、F2.8, 1/25s)
1-2:「フジキャビンの先生」、フランス・ルノー4CVのお尻
上の、あまりにも質素なフジキャビンには、「先生」がいた。
第二次世界大戦後のフランスでは、すでに庶民のための優れた車がいくつか作られていた。これは、ルノー4CV。
CVとはエンジン容積の単位で、フランスでは自動車税の税額の区分になる。同じくフランスの庶民の車としてたいへんな傑作だったシトロエン2CVは、このルノーの半分の容積のエンジンだったことになる。
シトロエン2CVがフロントエンジンで前輪駆動だったのと違って、このルノー4CVは、リアエンジンで後輪駆動だった。エンジンが車体の後部にあり、 その熱気を逃がすために、まるで昆虫の身体の一部のようなエンジンカバー(フード)が着いていた。
このルノーもなかなかの傑作で、約750ccほどの小さな水冷4気筒エンジンながら、卵形のモノコックボディーが軽いこともあって、なかなか俊足であり、燃費もよかった。フランスでは30年間も作られ続けて850万台を売ったほどだ。
また、このルノーは日野自動車で国産化され、日本国内でも広く使われた。当時の日野自動車の資料によれば、748ccの水冷4気筒エンジンで21馬力/4000rpm。車重は560kg、最高速度87km/hとある。これが上の写真だ。しかし、当時想定されていた自家用車の需要はごく少なく、タクシー用途がほとんどであった。はじめはノックダウン方式で、フランスから輸入された部品を組立て、のちには部品も国産化された。
後部の窓の下に着いているキャップは、中央が水冷エンジンの冷却水、右はガソリンの注入口であ る。
左の図は1957年に製造された当時の日野ルノー(PA-57型)のカタログから。この狭い車内に4人を押し込むための苦労が偲ばれる。また「室内用後写鏡」(ルームミラー)、「警音器」(ホーン)など、いまでは全く使われなくなった懐かしい日本語が使われているのもこのカタログから読みとれる。
私が尊敬する南極科学者(地球電磁気学者)の小口高さんは、国産化されたものではない、フランス製のルノー4CVを持っていた。東京都練馬区の西部にあるお宅から文京区本郷の東大地球物理学教室まで約20kmを、裏道ばかりを通って通っていたのを覚えている。
国産化されて追加された運転席側のドアの内張りがなく、そこには、厚さ20cmを優に超えるものが入る巨大なドアポケットがあり、運転席回りも、国産化でつけられた余計な装飾が一切ない、質素だが機能的なレバーやスイッチが付けられていた。
右下の写真はフランス製の、オリジナル・ルノー 4CV 。左上の写真にある日本で国産化されたのよりも後ろの窓が小さい。また、バンパーも小型で余分な飾りがないし、日本でつけられた、ごてごてしたクロームメッキの飾りがない。また、テールランプも違う。しかし、いちばん違っているのは、後ろドアのすぐ後ろにある、腕木式の方向指示器だ。

また、国産化されたものでは、エンジンフードの上に二つの注入孔があるが、オリジナルはひとつしかない。ガソリンと、ラジエターの冷却水の注入孔だが、ラジエターのほうを、あとから付け足したのであろう。
このフランスのルノーを撮影したのは1984年7月、フランス・パリのグラン・パレ展示場で開かれた「自動車の生誕100年展」であった。
なお、日野自動車は、このルノーの国産化で学んだあと、同じリアエンジン方式の純国産車、コンテッサを作った。
【追記】 1961年のことだった。エンジンは水冷900cc4気筒で、とてもよく走る車だった。ドアは4ドア。デザインはルノーとはまったく違うものだった。私の叔父がこの車を持っていて、よく、乗せてもらった。
当時の日産も英国のオースチンを1955年から1960年までノックダウン方式で国産化していたが、その後の1959年から作ったブルーバードは、国産化していたオースチンA50とよく似ていたのに対して、このコンテッサは、リアエンジン方式を採っている以外は、ほとんど「師匠」のルノーに似ていなかったのは立派なものだ。
そして、1964年。エンジン容積が1300cc(55馬力)になった二代目のコンテッサは、日野自動車が総力を挙げて作った名車だった。ドアは4ドア。
やはり水冷4気筒リアエンジン方式で、当時の国産車には見られない、優雅な車体と、鋭敏なステアリング特性と広い室内とを持っていた。
私は以前、中古を買って所有していたことがある(右の写真。1970年に撮影)。日野自動車の意気込みに反して当時は人気がなく、中古車で4万円だった。
しかしが、鼻先が軽く、まったくのニュートラルステアで、ハンドルを切ったとたんに、車体全体が真横に動く感じは、その後のどんな車にもなかった。もちろん、限界近くなれば、単純なリアのスウィングアクスルとリアエンジン特有のオーバーステアは出たが。
この車のシリンダーヘッドを外して、吸気ポートの内側を滑らかに磨いて、吸気の流れをよくするなど、私がいろいろエンジンをいじった車でもあった。
しかし、日野は弱小メーカーの悲しさで、販売力が追いつかず、日野自動車がトヨタの傘下に入ったことによって、乗用車生産から撤退させられてしまった。トラックしか作らなくなって、日野自動車の志気は落ちたといわれている。
日野自動車と同じように、当時の日本では、英国のヒルマンをいすゞ自動車が、また同じく英国のオースチンを日産自動車がノックダウンから始めて、国産化の道を歩んでいた。
(日野ルノーは2005年にトヨタ自動車博物館で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは36mm相当、F2.8, 1/30s。フランスのルノーの撮影機材はOlympus OM1、レンズは Tamron Zoom 35-70mm f3.5-4.5。フィルムはサクラカラー R200 ネガフィルム。撮影はフランス・パリのグラン・パレ。コンテッサ900は2012年に、東京・八王子の日野オートプラザで。撮影機材は Panasonic DMC-G2。レンズは 36mm相当、F4.0, 1/60s, ISO200)
1-3:お尻の巨大さは、このタトラにはかないません。
フジキャビンもルノーも、リアエンジンを収めるための、愛嬌のあるお尻を持っていた。しかし、このチェコ製のタトラ・サルーン・モデル77aの巨大なお尻には脱帽するしかあるまい。
しかも、このお尻は、まるで飛行機の垂直尾翼のようなフィンまでついている。
このタトラは、1936年製。当時のタトラは、時代をはるかに先取りした、6人乗りのこの大型乗用車を作っていた。世界のどのメーカーよりも、すぐれた車であった。
それにしても、なんと巨大なエンジンフードだろう。積んであるエンジンも、上のルノーよりもずっと大きい空冷V形8気筒、3,380cc、出力70HPとはいえ、このフードは、ポルシェやフォルクスワーゲン・ビートルよりもずっと大きい。後輪のホイールアーチを覆うカバーといい、この巨大なフードといい、エアロダイナミックスを、当時の車としては極限まで考えたデザインだった。
このタトラの後部のエンジンフードには、上のルノーに倍加したくらい一面のルーバーがあ り、真ん中の「垂直尾翼」と合わせると、まるで恐竜の背中のような光景になった。
【追記】2013年6月に、WSJ (Wall Street Journal)のウェブに、米国のテネシー州ナッシュビルにあるLane Motor Museumが所蔵している1937年型(WSJには1938年型とある)のタトラT97の写真(右)が出た。この写真だと背面がよく見える。
キャビン後部に出っ張っているのは、空冷リアエンジンの冷却のための空気取り入れ口であろう。後部の窓はフィンの左右にひとつずつあるが写真では右側のものしか見えていない。
このモデルの背面は、ニュージーランドの1936年型のタトラT77aとよく似ている。しかし、フロントガラスが一枚の平面だけになったり、フロントの中央のヘッドライトがなくなったりなど、簡素化されているところがある。前輪のホイールキャップは同じもののようだ。なお、このタトラT97はT77aの廉価版のようで、エンジンも小さく、4気筒1749ccで40馬力だった、しかし、この空力デザインのおかげで、最高速は130km/h、巡航速度も110km/hに達することが出来た。これは当時としては大変な高速であった。
じつは、SOHC (Single Over Head Cam)エンジン、バックボーンフレーム、スイングアクスル式の4輪独立懸架、空冷エンジン、リアエンジン方式、流線型の車体など、その後の世界の乗用車に引き継がれた革新的な技術は、みなタトラに発している。
このタトラ77aも、サスペンションは、前は横置きリーフスプリングの2段重ね、後ろはスイングアクスルと横置きリーフスプリングによる4輪独立懸架だった。日本車でいえば、すべての乗用車が4輪独立懸架になったのは、タトラから半世紀も後の、つい1980年代のことであった。
また、前部の中央には第三の前照灯があり、これは、ハンドルに連動して進行方向を照らす機構になっていた。これも時代をはるかに先取りしていた。かつてヘッドライトが3つある車はあったが、照射の向きは固定されていた。
右の写真に見られるように、フロントウインドは中央と、左右の3枚つなぎになっている。当時は曲面ガラスは作れなかったから、視界を広くするための工夫だった。
正確に言えば、このタトラ77aは、1934年に発表された、タトラ77が1935年に改良されたもので、77と77a合わせて250台あまりしか作られなかった。世界的な珍車である。
私が見たときには、この車はスクラップ寸前を「救出」されたばかりなのか、ツヤもなく、前のバンパーやワイパーアームもなく、レストアの途中のように見えた。
じつは、この時代は、過去、チェコがもっとも輝いた、しかし、ごく短い期間であった。
この時代のチェコは、17世紀の宗教戦争でカトリックのハプスブルグ家の勢力下に置かれてから3世紀、第一次世界大戦でハプスブルグ家のオーストリア・ハンガリー帝国が崩壊して、ようやく独立を果たして、当時の欧州でももっとも進んだ民主主義を実現した理想の国だったのである。当時のチェコの民主主義は、米国が自分の国益のために、中東や中南米に押しつける「民主主義」とはまったくちがう、本質的で良質のものだった。
そのときの指導者は初代チェコ大統領になったトマーシュ・ガリッグ・マサリクだった。バーナード・ショーは「もしもヨーロッパ連合を作るとしたら、その大統領としてはマサリクがなるべきだ」と主張したと言われている。
このころのチェコは精神も文化も輝いていた。そして、ヨーロッパ屈指の工業国にもなった。その「作品」のひとつが、この先進的なタトラだったのである。しかし、この輝きも、わずか20年で、ヒットラー率いるドイツにチェコが占領されて、地獄の日々をむかえることになってしまった。
【追記】1939年に第二次世界大戦が始まり、チェコはドイツに泥足で踏み込まれてしまった。そして、このタトラも、ドイツのフォルクスワーゲンに似ているという(ほとんど言いがかりの)理由で、生産を止めさせられてしまったのである。
なお、タトラは、乗用車を作るのはやめてしまったが、現在でも大型トラックではヨーロッパを代表するメーカーのひとつである。
(1994年1月に、ニュージーランド・ウェリントン郊外のサウスウォード自動車博物館で撮った。南半球最大の収集を誇っている自動車博物館である。撮影機材は、Olympus OM4、レンズは Tamron Zoom 28-70mm f3.5-4.5、コダクロームKL200)
2-1:敗戦国日本の「庶民のための車」その2・フライング・フェザー (1954年)
この車も、上のフジキャビンと同じく、富谷龍一氏の設計になる。ただし、作ったメーカーが違い、住江製作所(日産車のボディーを作る工場)だった。
タイヤは細く、ほとんどオートバイ(バイク)のタイヤである。スポークもまるで自転車のようだ。これは、重量物運搬用のリヤカー(自転車や人力で牽引する二輪の荷物車)のタイヤをそのまま流用したものだった。
名前のように、出来るかぎりの軽量化を図った車だ。屋根は布地(キャンバス)だし、バンパーは、まるで自転車のフェンダーなみの薄い金属である。2シーター(2座席)である。
しかし、こちらはエンジンは350cc、12.5馬力で、V型空冷2気筒のOHVエンジンだった。ヘッドライトは2つ、タイヤは4つあり、車体の長さは277cm、幅は130cm、車体重量は425kgあった。
上のフジキャビンと同じく、この車も時代よりは早く世に出すぎた。1954年に発表され、生産されたのは1955年の1年だけで、生産台数は、200台にも達しなかった(一説には48台というものもある)。 当時の価格は38万円だったが、庶民に手が出る値段ではなかった。
(2005年に、愛知県愛知郡長久手町のトヨタ自動車博物館で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは39mm相当、F2.8, 1/15s)
なんとも不器量なハンドルと、その軸(ステアリングポスト)の上に、これほど実用一点張りのスイッチはない、というほど簡素なホーンボタンが付いている。
ライトのスイッチはダッシュボードの右端に見える。ハンドルの右隣に駐車ブレーキのレバーがある。つまり、自動車に必要なものは、簡素だが、すべて揃っていたのである。
メーターは左が速度計、右は電流計である。速度計は100km/hまで刻まれているが、まさか、そこまでの速度は出なかっただろう。
電流計は、電池の充電状態を監視するためで、当時の電装品や電池の品質からいえば、運転者がいちばん気にしなければならなかった計器である。
じつは、このハンドルは、フランスの戦後の名車、シトロエン2CVのプロトタイプのハンドルと瓜二つである。偶然の一致なのか、欧州の小型車を研究していた富谷氏が、独創性を発揮できなかったのか、いまとなっては分からない。
(2005年にトヨタ自動車博物館で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは36mm相当、F2.8, 1/50s)
3-1:敗戦国日本の「庶民のための車」その3・コニー・グッピー (1961年)
これは、上の二つの車よりはあと、1960年代の車だ。1962年にはモノコックボディーでフラッシュサーフェスのブルーバードP312型が日産自動車から出ていた(1959年から発売されたP311型を改良したもの)が出たから、日本の自動車の技術が、あ ちこちで芽を出したころの車の一つである。
この車は、愛知機械工業が作った。下の5-1にあるスバル(富士重工)と同じく、戦時中は飛行機を製造していた工場が母体になった会社だ。
そのせいか、 この車は、当時としては先進的な4輪独立サスペンションや、岡村製作所のトルクコンバーターを導入したクラッチペダルのない2ペダル方式など、新しい技術を使っていた。
会社は三輪車のトラックで業績を伸ばし、1959年には軽自動車の3輪トラックに進出した。業界で初めて丸ハンドル(下の4-1を参照)を採用した軽自動車「ジャイアント・コニー」だった。そのエンジンは当時の軽自動車の枠、360ccだった。
その後、1961年になって、軽自動車の枠よりも小さな、つまりなるべく安く、軽くした軽トラックがこのコニー・グッピーだった。当時流行っていた二輪のスクーターからの乗換需要を期待したものだった。
コニー・グッピーは軽トラックとしては初めてのピックアップトラックだった。そもそもは積載量100kgの小型のトラックとして作られたものだが、この写真のものだけは、屋根を切って、2シーターのオープンカーに改造されている。
エンジンは2サイクルの空冷単気筒。199ccで11馬力。当時のブルーバードは1200ccで55馬力だったから、ずっと非力だった。しかし、22万5千円という、ブルーバードの半額以下という低価格を売り物に、約5000台を売った。しかし、庶民に手が届く価格ではなかった。わずか1年あまりで生産は中止されてしまった。
小規模メーカーだった会社は生き残ることが出来ず、1965年代には日産自動車と業務提携、翌1966年からサニー用A型エンジンとトランスミッションの生産を開始した。1970年代からは日産車ダットサン・サニートラックの生産を始めるに至った。資本主義の弱肉強食の世界である。なお、1990年代に発売された日産の初代バネットは、この愛知機械が設計したもので、愛知機械が作って売っていたコニーとよく似た設計だったといわれている。会社としての最後のあだ花であったのだろう。

車の全長は263cm、幅は126cm、重さは275kgであった。 上のフライングフェザーとほぼ同じ大きさだが、ずっと軽かったことになる。
小型車には小型車のデザインがあるはずで、フジキャビンと同じく、この車のデザインにも志が感じられる。
【2017年12月に追記】 凝ったメカニズムも理解されず
コニーは、その後、「コニー360」という軽自動車のライトバンとピックアップを作って売り出していた(右の写真はライトバン)。1962年から1970年まで製造販売していたもので、後半は日産自動車の傘下に入ってからである。
当時の軽自動車の車体の長さの枠としては一杯である 299.5 cm、全幅も 130 cm だった。
メカニズムは、最高速度80km/h弱なのに、とても凝っていた。たとえば、アンダーフロアエンジンを採用して、エンジンを縦置きにし、エンジンの潤滑には当時レーシングカーにしか使われていなかったドライサンプ方式を使い、オイルパンを持たなかった。ドライサンプとは、オイルタンク別体式で、つまりエンジンの高さを極力低くして居住性と積載性を向上させていた。エンジンは軽自動車枠におさまる空冷4サイクル水平対向2気筒OHV 354cc で、18.5馬力、1967年以降は20.6馬力に上げた。だが、これらのエンジン出力は当時の軽自動車にとっては一般的な数字だった。
また、 ステアリングギア形式は当時の欧州の最新鋭車なみのラック・アンド・ピニオンを使っていた。

そして、ボディデザインは、当時流行のフラットデッキスタイルをいち早く取り入れ、内部を広くして居住性も改善されていた。
だが、売れなかった。 大きな原因は「当時流行」のフラットデッキスタイルだったが、一方で飽きられやすい、平凡で特徴のないデザインだったことがある。とくに後部(左の写真)は、あまりに芸がなさ過ぎる。隣に並んだスバル360のユニークさとは大いに違ったのが敗因である。
下の5-1のスバル 360 と同じく自転車にぶつかってもへこみそうな細いクロームメッキのバンパーを使い、車重は575 kg だった。
また、当時、軽四輪分野ではホンダ、ダイハツ、スズキなどが社運を賭けてライトバンに乗り出していたので、各社の競争が激しかったこともある。ホンダは1967年、N360のライトバンである「LN360」などを出したし、先行していたスズキやダイハツもシェアを守るためニューモデルやパワーアップ版を相次いで登場させた。中小メーカー・コニーの凝ったメカニズムは当時の商用車の消費者にとってのメリットとしては理解されなかったのである。
(コニー・グッピーは2005年に愛知県愛知郡長久手町のトヨタ自動車博物館で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは49mm相当、F2.8, 1/15s、コニー360は2017年12月。東京・清瀬市の加藤自動車で。撮影機材はOlympus OM-D E-M5)
4-1:敗戦国日本の「庶民のための車」その4・ダイハツ・ミゼットMP5貨物車(1963年型)
焦土から日本が立ち上がったのを支えたのは、じつは乗用車ではなくて、物流を担ったトラックであった。それも、小企業や商店の荷物輸送のためには、小型で安いトラックが活躍した。
これは大阪のメーカー、ダイハツが作ったダイハツ・ミゼットである。前1輪の3輪車で、四角くて大きな荷台をとり、しかも安価にするために前を1輪にしたデザインだ。
そのうえ、添乗や荷扱いのために、助手を乗せなければならない。そのために、かなり無理をして丸ハンドルを導入し、二人乗りとしている。また、当時で言う「全天候キャビン」も採用した。運転席の横側が吹きさらしで、雨が降り込むようなそれまでのキャビンと違って、ドアもガラスもある運転席だったからである。
それまでは、このミゼットの旧型(1957年に発売されていたDK型)を含めて、バイクのようなバーハンドルの一人乗りの3輪トラックばかりだったのが、この最終型のミゼットは、それなりの「高級感」をアピールするのに成功して、ベストセラーになった。
写真のMP型は1959年10月に発売された。ハンドルはDK型のバーハンドルから丸ハンドルになった。車体寸法は全長2970mm、全幅1295mm、全高1455mmだった。
エンジンは最初は250ccの単気筒、2サイクルエンジンだった。その後、軽自動車の枠一杯の360ccになった。たくさん売れて、みんなの役に立ったという意味では、これこそ日本の国民車であ った。

もちろん、急ハンドルを切ると転覆するという3輪車として避けられない欠点もあった。しかし、そんなぜいたくは言っていられない時代だったのである。
なお、右上の写真のミゼットは、ヘッドライトの後方のフェンダー部分に四角いサイドマーカーランプがついた新型である。それ以外の基本形は変わっていない。
このミゼット三輪車の生産は1972年に終わったが、その直前のモデルであろう。生産累計は31万7152台といわれている。ちなみに初代ミゼットの生産開始時の1957年の全国の自動車保有台数は二輪車も含めてもたった177万台だったから、ミゼットは驚くべき売れ行きだったといえるだろう。
左は、その運転席。当時としては「高級車」であった丸ハンドルがあり、シフトレバーは、まるで現代のフェラーリのように、床にシフトゲート(金属のガイド板)がある。そう言えば、球状のシフトノブもフェラーリ似である。前進3段、後進1段である。
スイッチやメーターは、必要最小限のものしかない。なお、右から二番目はスイッチではなく、イグニションキーの鍵穴である。
ダッシュボードにある蓋のようなものは、多分、夏のために使う、外気取り入れ口であろう。ここから手を突っ込んで、ボンネット部分にある外気導入口を開けるのに違いない。

そして、ルノーを国産化したり、コンテッサを作っていた日野自動車も、1961年からこの軽三輪市場に乗り込んでいた。右の写真の日野・ハスラーである。といっても、製造していたのは三井精機工業で、日野ヂーゼルのブランドで売っていたものだ。なお、三井精機工業は「オリエント」という商品名で三輪車を製造して売っていた。
デザインは2012年に亡くなった工業デザイナー柳宗理で、たしかに、それなりにあか抜けてかわいいデザインである。
ハンドルは上のミゼットとは違って、その前の時代のバーハンドル、一人乗りだった。上の丸ハンドルで二人乗りのミゼットよりも遅れてバーハンドルの軽三輪を発売したのだから、ほどんと売れなかった。
写真はハスラーEF11型。全長は268cm、全幅は125センチ、積載量は350kgだった。
(上のミゼットの写真は2005年に、愛知県愛知郡長久手町のトヨタ自動車博物館で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは41mm相当、F2.8, 1/25s、右上と左のミゼットの写真は2010年11月に、東京都練馬区の「ふるさと文化館」で。撮影機材は Panasonic DMC-G1。右上はレンズは36mm相当、F3.9, 1/30s、ISO (ASA) 500、左はレンズは36mm相当、、F3.9, 1/30s、ISO (ASA) 500。下の日野ハスラーの写真は2012年2月に、東京・八王子の日野オートプラザで。撮影機材はPanasonic DMC-G2。レンズは 44mm相当、F4.6, 1/60, ISO125)
4-2:ダイハツCM型。”法律の抜け道”ながら、当時の物流を支えた働きもの
上のダイハツ・ミゼットよりも大きな三輪トラック(オート三輪)も、ダイハツと東洋工業(現マツダ)の両社で作られて売られた。これは、ダイハツのCM型。丸ハンドル、二本ワイパー、3人乗りの1.25〜2.0トン積みのトラックだ。東洋工業も、同じサイズのトラックを作っていた。
この三輪トラックは、もちろん同じ積載量の四輪のトラックよりもずっと安いのが取り柄で、大いに普及して、1950年代から1960年代までの日本の物流を支える大事な輸送手段だった。
三輪トラックは、安いばかりではなく、前輪の切れ角が大きいので回転半径が小さく、小回りが利く。前輪の操舵装置も簡単でコストも安い。そのうえ、四輪車とちがって、法律の”抜け道”の有利さも生かせるトラックでもあった。
それは昭和20年代末期(1950年くらい)まで、エンジンの容積だけは小型車枠があったが、車体の幅や車体の長さについては、なんの制約もなかったことだった。
このため1950年代初頭以降、「ユーザーの要求に応える」という名目で、生産していた会社の競争が激化し、オート三輪の巨大化と長大化が進んだ。そして、ついには幅1.9m、荷台の長さは”13尺”(約3.9m=当時は荷台の長さを尺で表すのが普通だった)、車体の全長6m弱、という、もっと上位の4輪トラックを上回るようなオート三輪までが現われることになった。積載量も最大2トンに達した。
もちろん、三輪車は四輪車よりも安定が悪く、転覆しやすい。また、舗装道路が限られていて穴ぼこだらけだった当時の道では、道路の穴をまたぐことが出来ないので、乗り心地も悪かった。しかし、安さと便利さには勝てなかったのである。
オート三輪がこのように際限なく巨大化したため、当時の運輸省は1955年に「小型自動車扱いのオート三輪は、現存するモデル以上の大きさにしてはならない」と歯止めを掛けた。つまりこの写真のオート三輪が最大サイズとして固定されたのであった。
なお、ダイハツ三輪車の形式は「CO型」が最大積載量2屯、「CM型」が最大積載量1.25〜1.5屯。それに続く数字は荷台長さで、「8」が8尺(2.4m)荷台、「10」が10尺(3.1m)荷台、「13」が13尺(3.9m)荷台。その後の記号は荷台形式で、「なし」が低床一方開き、「T」が三方開き、「TL」が低床三方開きだった。つまり写真のトラックはCM8ということになる。

しかし、上記のような安全性と、1965年にはそれまであった「三輪車運転免許」が廃止されたこと、そしてオート三輪の装備も競争で豪華になっていって値段的にも四輪トラックに近づいていった。
【追記】 そこにとどめを刺したのが「販売のトヨタ」が売り出した廉価版の四輪トラック「トヨエース」だった。トヨエースはキャブオーバー型で、エンジンは1000ccだったが、その値段は半年ごとに戦略的に切り下げられ、1957年には46万円と、オート三輪と同じ価格にまで下げられた。こうして、1953年にピークを迎えていた全オート三輪の販売は1957年には約10万台に下がり、四輪の全トラックに負け、1972年にダイハツが、そして最後まで残った東洋工業も1974年に生産を中止した。
【2019年12月に追記】下の写真に見られるように、そのトヨエースも、ドアのヒンジなどはとても安く作られていた。まるで軍用車である。
しかし、生産停止後30年以上経った今でも、オート三輪の不格好さを愛でるマニアも結構いる。
(上の写真は2008年10月、長野県長門町で。ナンバーが着いた実動車だった。なお、オート三輪には、もともと前部にナンバープレートはない。撮影機材はPanasonic Digital DMC-FZ20。ISO (ASA) 80。レンズは36mm相当、F4.0、1/400s)
【2018年9月に追記】伊豆半島にある伊豆長岡(伊豆の国市)の温泉宿「弘法の湯」で、とてもきれいにレストアされたダイハツのオート三輪があった。ここで使っていた車で、政策的に安値を着けた4輪トラックに負け始めた1963年に購入して、中小企業を支えてきたのだろう。
この頃は、もちろんエアコンもクーラーもないから、ボンネットの上面や足元が外気を取り入れるために、大きく開くようになっている。その「蓋」が見えるだろうか。
(下の写真は2018年9月、静岡県伊豆の国市で。トヨエースのドアヒンジは2019年12月、東京・お台場のトヨタmega webで。撮影機材はOlympus OM-D E-M5)
4-3:小型三輪車が、1990年代にまだ輝いていました。中国の「庶民のための車」
上のダイハツ・ミゼットのように、焦土から日本が立ち上がったのを支えたのは、じつは乗用車ではなくて、三輪車だった。このミゼットなど、小型の三輪車が活躍したのは1960年代だった。1972年には、軽4輪のダイハツ・ハイゼットに席を譲って、ダイハツ最後の三輪車としての生産を終えた。
しかし、中国では1990年代に入ってからも、写真のような小型三輪車が、底辺の物流を支えていた。持ち主にとっては、かけがえのない宝だから、ぴかぴかに磨き上げられていて、翼のついたヘッドマークも、誇らしげだ。ヨーロッパの小型の三輪車が、「下駄」のような実用車だったのと、大事にされ方がちがっているのであ る。
(1991年に、中国・北京市内で。撮影機材はOlympus OM4Ti。レンズは Tamron Zoom 28-70mm F3.5-3.5。フィルムはコダクロームKR)
タイの軽三輪タクシー「トゥクトゥク」はこちらに。
5-1:日本の「庶民のための車」その5・日本としては名車だったスバル360
上の3-1までの国産車たちが庶民には高価すぎたことと、車としては未熟で、ほとんど実用には耐えなかったのと違って、戦後の日本で初めて作られた実用になる乗用車が、このスバル360だった。最初のモデル(K111型)は1958年に出た。戦時中の飛行機メーカーだった富士重工が作った。飛行機屋らしい設計があちこちに見てとれる軽量で高性能の車だった。
これは、当時の政府の「国民車構想」に合わせたもので、大卒初任給が1万3000円の当時、42万5000円という価格で、ほかの車よりもずっと安かった。
一見、ドイツの国民車フォルクスワーゲン・ビートル(カブトムシ)に似ている。空冷のエンジンを車体後部に置き、後輪を駆動するRR方式であることも同じだ。 これらが似ていることは日本人の独創性の限界かもしれない。
なお、フォルクスワーゲンは、ビートルの車台をそのまま生かして、ワンボックスの「マイクロバス」(右下の写真)を作った。エンジンが車体後部にあるので車体を前後に貫くプロペラシャフトも不要になり、広大な車室(荷室)が確保できる。スバルはそこも真似して、「スバル・サンバー」を作った。このサンバーはスバル360が後継車に代わってからも生き続け、富士重工が軽自動車の製造をやめた2013年まで製造や販売が続けられた。
しかしスバル360は、それまでの日本車と比べれば、段違いによくできた車であった。卵形のモノコックボディは軽くて丈夫なうえ、大人4人がそれほど窮屈ではなく座れるという、外寸サイズの割には居住性も高かった。これは、エンジンの配置や、サスペンションの形式や配置を巧みに工夫した設計の妙であった。天井とリアウィンドウは、軽くするためにプラスチックである。車体重量は、わずか385kgであった。
なお、外寸サイズは、当時の軽自動車の枠いっぱいの長さ3メートル、幅1.3メートルであった。 右下の図(『CG』2008年11月号)と左下の図(杉山夙『スバルは何を創ったか--スバル360とスバル1000”独創性"の系譜』)のように、じつにうまく”詰め合わせて”いるパッケージデザインである。
この軽量化のおかげで、当時の軽自動車の枠であった360ccのエンジンでも、当時のレベルとしては十分に走らせることができた。エンジンは空冷2気筒、エンジンの出力は16馬力/4600rpm、公称最高速度は83km/hであった。 この後数年にわたって、このスバル360をしのぐ性能や居住性を持つ車は出なかった。
メーターはスピードメーターひとつだけ。シートも金属パイプの枠に布を張っただけ。燃料計もなかった。ボンネットの上部、前面ガラスの前にある四角い蓋は、暑い日に開けると風を取り込む仕掛けである。燃料計も警告ランプもない代わりに、18リットル入りのガソリンがなくなってエンジンがストップすると、車を降りてエンジンフードを開け、燃料コックを「通常」から「予備」に切り替えることによって、ガソリンの予備タンクにある残りの2リットルを使って走る、という単純な仕掛けであった。
なお、実際には、エンジンが2サイクルだったから、「混合油」と言われたガソリンとエンジンオイルをあらかじめ混合した燃料だった。この2サイクルエンジンはエンジンの容積や重量のわりに出力やトルクが大きかったので、他メーカーにも広く使われたが、エンジンの構造上、吸気側の混合気の一部が排気側に吹き抜けてしまうので、その後の排気ガス規制をクリアーできず、姿を消している。
私が初めてこの車に接したのは、私が大学院生のころ、指導教官だった浅田敏氏が持っていたスバル360に乗ったときだった。燃費がいい車だったから、予備の2リットルになってからも結構な距離を走るので、浅田氏は、燃料補給を忘れたままストップしてしまうことがよくあった。
「出足では、隣に並んだタクシーには絶対に負けない」というのが浅田氏の自慢であった。結構なスピード狂というべきだろう。都内の一般道で、ミニカーに乗った白髪の老紳士が、アクセルペダルを床まで踏みつけて、エンジンの音が変わるまで(*)回転を上げて全力加速をしているのを見て、タクシーの運転手は、さぞ驚いたことだろう。
*)2サイクルのエンジンだったから、回転を上げすぎても4サイクルエンジンのようにカムシャフトやバルブまわりから苦しそうな音が出る(バルブのサージングとかバウンシングと言われる現象)ことはなかったが、「回転数を限度まで上げると、突然、力が抜けてしまうのだよ」と浅田敏先生は話しておられた。
なお、このバルブ(吸入バルブと排気バルブの2種がある)のバウンシングを防いで、エンジンの許容回転数を上げる簡単な手法は、バルブを押さえているバルブスプリングを強いものに取り替えることだ。
私も、昔乗っていたコンテッサ1300(これも名車だった。日野自動車が渾身の力を傾けて作ったが、トラックメーカーの哀しさで、乗用車の売り上げは伸びなかった)のシリンダーヘッドを自分で外して、バルブスプリングを取り替えたり、吸入する空気の抵抗を少なくするために、吸入ポートを磨いたりしたものだ。

この頃の車は構造が単純だったし、当時の車の通例として、よく故障もしたので、私たちも、地球物理学教室の前庭で、よくこの先生のスバル360を分解して、部品をまわりいっぱいに拡げて故障部分を修理したものだった。
また、私たちがいた地球物理学教室を車で訪れた東京大学地震研究所の萩原尊礼所長の自家用車(英国のモーリスマイナーだった)のエンジンがかからなくなったので、みんなで車を押してエンジンをかけるようなことも、よくあることだった。
(写真いちばん上は2005年6月と、右は2014年3月。東京・清瀬市の加藤自動車で。上の写真では高く突き立ったボンネットミラー、自転車にぶつかってもへこみそうな細いクロームメッキのバンパー、薄くてちゃちなフォグランプなど、この車はオリジナルの状態をよく保っている。しかし、自走できなくなってしまったのか、牽引されるためのヒモが結びつけられているのには、なんとも哀れを誘う。また下の写真では(片方の眼の瞼がなくなっているが)チョコレート色が意外に似合うスバル360。なお、隣のハダカにされたスバル360では、外板の構造や骨格がよくわかる。真ん中の写真のフォルクスワーゲン・マイクロバスは2014年3月、東京・早稲田で)
6-1:名車スバル360の改良を試みて無惨にも失敗したスバルR2
スバル360は、はじめは必要最小限のメーターやアクセサリーしか着いていなかった。ドアの内張りもなく、ドアの内側には下部にポケット状のプラスチック板があるだけだった。このため、このドアポケットには、厚さにして20cm以上の巨大なものが入れられた。
しかし、年とともに、スバル360も「豪華」になっていった。燃料メーターや、ドアの内張りも着き、ヘッドライト周りにも瞼(まぶた)状の飾りが付けられ(上の5-1は、この瞼が着けられた後期モデルである)、豪華さを求める大衆に媚びる「改良」が続けられた。
もちろん、それとともに、車重は増え、軽飛行機を操縦しているような運転者との一体感が失われていったことも確かなことだった。
それには、スバル360を追撃してきていた軽自動車のマツダ・キャロルや小型自動車の日産ブルーバード(1960年のP311型や1962年のP312型)やトヨタ・パブリカなど、「小さくても豪華な」車の影響が大きかった。小さな車には最大限の実用性を求めて見かけの「豪華さ」を求めない欧州の大衆と比べて、日本の大衆は成熟していなかったのである。
そして、スバルは営業分野に押されたのか、初心を忘れた。スバル360をやめて、1969年に、二代目であるこのスバルR2に切り替えたのであった。 RR方式や車体の大きさはそのままであった。エンジンはアルミ合金製のシリンダーブロックに変更された。
しかし、なんという変哲のない車になってしまったのであろう。当時の流行であったフラッシュ・サーフェスや、広くて四角いボンネットを無定見に取り入れただけで、緊張感のないデザインに堕してしまった。しかも1971年10月、途中で空冷から水冷に変更されたエンジンのために、車体のフロント部分にラジエーターグリルが着けられたが、そのデザインも不評を買った。
なお、写真のR2は初期の空冷エンジン型だが、砲弾型のボンネットミラーや両側のゴム製のチンスポイラーなど、のちに発売になったSSモデルと同じ装備がオプションとして売られたものを着けている。(これは2010年現在、1985年型のレオーネクーペに乗っていらっしゃる愛媛県在住のzinさんからご指摘いただきました)。当時としては精一杯のおしゃれだったのである。
スバル360の「本家」であるドイツ・フォルクスワーゲン社が、ビートルから初代ゴルフへ、見事な転身を遂げたのとは対照的だった。初代ゴルフは、RR方式からFF方式(エンジンを車体前部に置き、前輪を駆動する)に転換し、極めてすぐれた居住性と一流の操縦性を得たのと比べると、このR2は、単に表の皮を着せ替えただけのようにしか見えない。(しかし、肥大化して質実剛健さをなくしていったその後のゴルフの変遷は、私には、やはり堕落に見える)。
じつは、このR2は、出初めこそよかったものの、その後、販売は急落した。初代のスバル360が12年も続いたのに、このR2は、わずか3年足らずで、次のモデルを出さざるを得なかったのであった。
スバルが再び名車と言われる車を出したのは、のちの1966年に発売したスバル1000(やエンジンを強化したスバル1300、1970年発売)になってからである。
【追記】 左の写真は、私が中古で買って乗っていたスバル1000。写真は1973年に札幌の自宅近くで撮った。
このスバル1000 (A12)は、コストを無視しているほどのぜいたくな設計だった。たとえば、デュアルラジエターやインボードブレーキは、性能のためには高価な部品をぜいたくに使っていたし、そもそも前輪駆動のための等速ジョイントも、このスバル1000がはじめて実用化したものだ。
当時はまだ前輪駆動が少なく、雪道では、もっと高馬力の他のどんな車よりも俊足だった。当時の北海道大学理学部の気象学の教授・孫野長治氏をはじめ、気象学教室の助教授と助手、そして地球物理学教室や低温科学研究所にも、日本全体ではマイナーだったスバル1000がとても多かった。
フランスのシトロエンの真似だが、この車のスペアタイヤはエンジンルームに入っていた。水平対向エンジンの上、運転手寄りのところに、水平に載せてあったのである。このためもあってトランクも当時の中型車よりもずっと広大だったし、後席の背もたれを外すことによって、ワゴン並みの積み込み能力も持っていた。
また、スペアタイヤがトランクの底にあるほかの車と違って、パンクしてタイヤを取り替えるときも、トランクの荷物を出さなくてもいい、とか、前面衝突したときに運転手の前のエンジンルームに水平に置いたタイヤがあるのは安心だとか、いろいろな利点もあった。この特長は、私が後に(いずれも中古車で)乗り継いだスバル1300 (A15)や、レオーネAM1(レオーネバン)、AM3(レオーネバン 4WD)、AA5(レオーネSTターボセダン)にも引き継がれていた。
(スバルR2は、2005年6月。東京都清瀬市の志木街道で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは53mm相当、F2.8, 1/125s)
じつは、このスバルR2には「偉大な」先輩がいる。右の写真にあるイタリアのフィアット500 (Fiat 500)である。 1957年に発売され、1975年に生産中止になるまでに世界中で340万台も売れた、大変なベストセラーだった。
この時代に、ヨーロッパの他の国でも、質素だが必要十分な性能を持つ、すぐれた車が作られていた。フランスではシトロエン2CVが累計で500万台を売ったし、フランスの対抗馬、ルノー4CV(1-2。ルノーR4)も30年間も作られ続けて850万台を売った。また、英国のオースチン・ミニは、もっぱら日本市場のために、2000年まで製造されていた。
このフィアット500も、RR方式だった。車体の長さは3メートル、幅は1.3メートルで、当時の日本の軽自動車とほとんど同じだった。エンジンは空冷直列2気筒OHVで、479ccだったが、後年は 499ccに拡大され、18馬力を生んだ。
日本やドイツと同じく、第二次大戦の敗戦国だったイタリアで、庶民のための、最小限度だが、しかし設計の妙で、十分な性能や居住性を持った車として作られた名車だった。可愛らしい顔つきやお尻と相まって、いまだに日本にもファンクラブがいくつもあるほどだ。
上の銀色のフィアット500は ドイツ・ブレーメンハーフェン市内で。ボンネットを止めているゴムのストラップはおしゃれのために後から着けたもので、オリジナルではない。
オリジナルは、左のルーマニアで撮ったフィアット500のようなものだった。 繁華街に止めておくだけでレストランの宣伝になる車はめったにない。
なお、このボンネットを開けてもエンジンが入っているわけではない。スペアタイアや、前席に座っている人の足が入るスペースが必要なために、リアエンジン車のトランクは、がっかりするほど小さいことが多い。
たとえば、初期のポルシェは、歯ブラシしか入れられない、と言われていた。
なお、このフィアット500の兄弟分の車にはフィアット600や、フィアット850がいる。
右の図右の図(『CG』2008年11月号)のように、フィアットのこの車も、うまく”詰め合わせて”いるパッケージデザインである。上のスバル360よりも、後席が高いところに座るようになっている。前がよく見えて閉塞感がない代わりに、頭上の空間がない。
しかし、フィアットFiatも、その後経営危機にさらされ、欧州各メーカーの生き残り競争の中で、売らんかな主義に堕落した。2007年5月に発売した「新型500」は、50年前に発売した「旧」500の外形だけを、しかも、みっともなくなぞっただけの、不格好な車として登場することになった。
昔の”なぞり”の事情はオースチン・ミニも同じだ。英国ローバー社の破綻とともにドイツBMWに買い取られたミニは、その後、外形だけノスタルジー、中身はBMWの安物セダンという新型ミニになった。
しかし、初代ミニを作った鬼才、アレック・イシゴニスの旧ミニ(右下の図。『CG』2008年11月号)とは違って、まず外形ありき、の消費者に媚びるデザインに堕した。内容の必然がないデザインは不毛である。新型フィアット500とともに、見かけの一見可愛らしさにすがろうとするのは、かつての日産Be-1やパオやフィガロと同じく、すぐ飽きられる。伝統ある欧州の自動車メーカーがすべきことではあるまい。
また新型ミニは、ストロークの少ないサスペンションの欠点を補うために、固いバネを入れたために、乗り心地は極端に悪くなってしまった。
1958年にスバル360を生み、その後、1969年にスバルR2を売り出すまでのスバル(富士重工)の開発陣が、この「旧」フィアット500を知らなかったわけがない。
当時の日本の他のメーカーと同じように、参考になりそうな外国の車を輸入して(*)、徹底的に分解して研究していたにちがいない。もっとも、これは当時の日本ではよくあること、たとえば、ニコンのようなカメラメーカーでも同じであった。

【追記】 じつは、この「習慣」は2012年現在も続いている。ドイツ・フォルクスワーゲン社のよくできた小型車「up!(アップ)」を、日本の自動車メーカーが多数買って、分解したり、自社のテストコースを走らせているという。
【2017年11月に追記】その後、日本で、この車を見た。東京・台場にあるトヨタ Mega Webというところに置いてあったフィアット500だ。
運転席には、この一つのメーターしかない。簡素なものだ。速度計のほか、オドメーター(累積走行距離)だけだ。
この速度計のメーターは右の写真のように、70MPH (112km/h)まで刻まれている。62くらいのところにある点は、エンジンの回転超過を示す赤ランプでも点くのだろうか。
速度計の中に見える赤い印は、それぞれのギヤで最も効率のいい速度を示しているのだろう。
なお、同じようなRRのチェコのシュコダは、こちらに。
(*当時の通産省が輸入して、国産車奨励のためにメーカーに提供したことも多かった。また、ノックダウンという、部品を欧州から輸入して、日本で自動車を組み立てる生産方式を奨励して、いすゞ、日産、日野が、それぞれ英国のヒルマン、同じく英国のオースチン、フランスのルノーを「国産化」していた時代でもあった)。
しかし、フィアット500の発売から14年も経って出したスバルR2が、フィアットを超えられないどころか、後追い、いや、正直に言えば、かなりの物真似にしかならなかったことは哀しい。
(上の銀色のフィアット500の写真は2004年10月。ドイツ・ブレーメンハーフェン市内で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは92mm相当、F2.8, 1/80s。下の赤いフィアット500の写真二枚は2012年11月、ルーマニアの古都シビウ市で)
6-2:フィアット500は初代だった先代も、かわいい顔をしたベストセラーでした。
この写真は1936年から1955年まで20年にもわたって製造された初代。上のフィアット500の先代に当たる。
このフィアット500も、大ベストセラー車だった。戦時中の生産中断があったが、それでも約12万2千台もが生産された。
この初代には「トポリーノ」(ハツカネズミ)という愛称がつけられている。
車としては、当時としてはなかなか高度のものだった。前輪独立サスペンション、当時としては一般的ではなかった全輪油圧ブレーキ、空気抵抗の少ない流線型のボディーなどだ。
なお、このラジエターグリルを流線型にしたのは、1934年に発売された、米国クライスラーのエアフローが先である。(このエアフローは写真の後方にも写っている)。
エンジンはサイドバルブ(SV)、クランクシャフトは2ベアリングという、当時としては普通の仕様ながら、上級の車なみの水冷4気筒で、、569ccの排気量から13.5馬力の出力を生んだ。なお、後期型ではエンジンは排気量570ccのOHV、16馬力のものに強化された。
なお、写真のようにラジエターグリルが傾いているために内部のラジエターをこのすぐ後ろに置けず、エンジンより後部の車室の直前に置いている。
見られるとおり、二人乗りだが、イタリアでは、この小さなクルマに無理をして4〜5人を詰め込んで走るのが当たり前のように行われていた。
このため、後輪のスプリングが折れるという事故が多発、フィアット車は、前期の固定式後車軸を支える板バネ(1/4カンチレバーリーフ)から、1938年には後車軸スプリングは1/2半楕円リーフに強化せざるを得なかった。
このトポリーノはフランスのシムカでも「シムカ5(サンク)」の名前で1937年から生産された。なお、フランスでは当時はまだこのサイズの「3CV」級のミニカーがなかったのでよく売れた。
しかし戦後になって、1946年に「ルノー・4CV」、1948年に「シトロエン・2CV」という、ともに大変な傑作の小型4ドア4人乗り大衆車が発売されると、2人乗りであったがゆえに急激に販売を減らして、このフランス製のシムカは、1950年ごろには生産が中止された(前述のように、イタリアでは1955年まで生産された)。
スペアタイヤは、写真のように、後部にはまっている。デザインの妙というべきだろう。
(2012年6月に、愛知県のトヨタ博物館で)
6-3:スバル360を追い落としたベストセラー、初代マツダキャロルも、やはり真似でした。
スバル360を追う他のメーカーのうち、マツダは「豪華さ」を売り物にした。軽量で質素、運動性能がいい戦闘機のようなスバル360に正面戦争を挑んでも、勝てないことがわかっていたことを踏まえての、いかにも日本人好みの戦術であった。それがマツダ・キャロル Carol (初代、KPDA型)だった。
まず、デザインは、当時のマツダが好評を博していた右下のマツダ・R360クーペのデザインの流れを汲む、可愛くて洒落たデザインだった。このほか、トラックや三輪のトラックや乗用車も含めて、当時のマツダのデザインは品がよく、日本人好みのデザインで売っていた。
右下のマツダ・R360クーペは、スバル360を追撃すべく、安く、また日本人好みのデザインを売り物にして1960年に発売された。この車は、マツダが4輪乗用車市場にはじめて参入した車だ。当時としては30万円という、当時のスバル360より安い、破格の値段だった。
安くするために、車体そのものは当時の軽自動車の枠一杯のサイズだったが、車室はごく小型にして、大人2人と子供2人の4人乗りがやっとだった。また、サイドウィンドゥとリアウィンドゥにはガラスの代わりにアクリルが使われていた。軽量化のためだ。
30万円という価格のため、発売当初は非常に高い人気を得たが、大人4人が座れるスバル360に追いついて、追い越すことは無理だった。
このため、マツダが次に作ったのが大人4人が(辛うじて)座れるキャロルだったのである。R360クーペは1966年まで生産が続けられた。
キャロルは、上下を別の色で塗り分けるツートーンカラーも豪華さを演出した。
そして ドアは4つ。これで後部座席への出入りは格段に楽になった。軽自動車としては初めてだった。1962年にはじめてキャロルが発売されたときは2ドアだけだったが、その後すぐの翌年から4ドアモデルが発売された。
そして、全長3メートルという軽自動車の制約の中で、後部座席を少しでも広くするために、右下の写真のように、後部窓ガラスを「後ろ上がり」の、普通とは逆の傾斜にした。これで、普通の後ろ下がりの傾斜の後部窓ガラスのスバル360にくらべて、いくぶん広くなったように見える。車体の幅は、当時の軽自動車の枠一杯の1.3メートルだった。
マツダはこの後部窓をクリフカットと称した。クリフは断崖絶壁という意味だ。しかし、この逆傾斜の後部窓ガラスは、じつは、左下の英国フォード・アングリアの明確なパクリであった。真似をできるものは臆面もなく真似をする、のが、いまに至るまでの日本の工業の常套手段だ。
ずっと後年、21世紀になってからも、フランスのプジョー Peugeot 307が、天井いっぱいのガラス天窓を備えた車を出してヒットしたら、たちまち、ホンダ・エアーウェイブやトヨタが真似をし、2008年初夏になると、かつては独創性を売り物にしていたスバルまでが、エクシーガ Exiga で追随した。
かつては、遅れた工業国が、先進工業国に追いつくための苦しまぎれの手段だったという弁解はあろう。しかし、それがいまだに続いているのは哀しい。
さて、そのせっかくの真似も、じつは、それほど後部差席を広くはしてくれなかった。右の写真を見て想像してもらえばわかるように、無理をして逆傾斜のガラスを置かなくても、ハッチバック(2ボックス)のほうが、むしろ車室を広くとれるからである。
スバル360でさえ、後部座席はキャロルにくらべて狭くはなく、しかも後部座席の後ろ、つまりエンジンの上に、結構深い荷物入れがあったほどである。
そのほか、マツダキャロルは、当時の軽自動車としてははじめての4気筒エンジンだった。容積は軽自動車の枠一杯だった360cc。スバル360は2気筒2サイクルの鋳鉄のシリンダーを持つエンジンだったが、マツダは水冷、4サイクルのアルミエンジンで、コストがかかっていた。しかし、2サイクルのスバルのエンジンにくらべて、いくぶん静かではあったものの、4サイクルであったためもあり、非力であった。
なお、両車とも、エンジンは車体後部にあ って後輪を駆動する、RR(リアエンジン、リアドライブ)だった。これは当時としては、車体のわりに車室を広くとれるデザインだった。
また、写真で見られるように、サイドの窓が最近の車と違って垂直に近く立っている。このため、車室は精一杯広くデザインされているのが分かる。
左のR360クーペも、RRだった。ただしこちらは2気筒で、強制空冷 76° V型エンジンだった。 OHV 4ストローク 356 cc、圧縮比 8.0で出力は16 ps / 5300 rpmだった。
その後、小型車では世界を席巻したFF(フロントエンジン、フロントドライブ)は、必須の部品である等速ジョイントに信頼性があってコストの安いものがなく、実用にはなっていなかったのであ る。
この、ややごてごてした、しかし一見可愛いキャロルは、ベストセラーになり、スバル360を蹴落とした。
どんな小さい車にも豪華さを求める日本人の好みを熟知していたマツダの勝利であった。そして、悪あがきした富士重工が作ったのがスバルR2だったが、これはさんざんの失敗作に終わった。
左が、マツダキャロルの「先生」だった、英国フォードの大衆車、フォード・アングリア 105E。一見似ていないようだが、この車の後部窓ガラスは、キャロルと同じように、というよりキャロルが真似したとおり、逆の傾斜になっている。
当時は、雨が当たらないので後方視界がいいともいわれた。なお、アングリアとは、英国のラテン語名である。
なお、アングリアは1939-1967の間に4世代の車が作られた。この105Eは1959-1967に作られたアングリアの最終モデルだ。
後部窓の逆傾斜だけでもみっともないのに、この車の目であるヘッドライトは、まるで蛙の目だ。横に引き伸ばされたラジエーターグリルも、しまりがない口を思わせる。
たぶん、このデザインは、1940年代後半の米国のスチュードベーカーを真似したかったのであろう。米国車としては珍しく、ごてごてした飾りが少なく、伸びやかなデザインだったスチュードベーカーをモデルにしたのにちがいない。
スチュードベーカーは第二次大戦直後の1947年に レイモンド・ローウィ(Raymond Loewy 1893-1986)のデザインになる新型モデルを発表して売り上げを伸ばした。 ローウィは工業デザイナーの草分けで、日本の煙草「ピース」もデザインした。当時、日本人の常識から言えば高額なデザイン料が話題になったものだ。
このローウィのスチュードベーカーは「どちらに向かって走っているのかわからない」などと評判がたつほど斬新で、世界的にもすぐれたデザインだった。彼は次のフルモデルチェンジに当たる1953年モデルもデザインしたが、その後、関係を絶った。それとともに、ビッグスリーの新車開発と値下げ競争によってスチュードベーカーはジリ貧の一途をたどることになる。
ところで、スチュードベーカーのデザインは、米国のフルサイズの大型乗用車にあって、はじめて映えるデザインだった。それを、このアングリアのような小型車に応用することは、所詮、無理だったのである。小型車には小型車のデザインがあり、それを無視した英国フォードのこのデザインには、本来持つべき、伸びやかさが感じられなくなってしまっている。
なお、このアングリア105Eのエンジンは 997 cc、4サイクル直列4気筒。ホイールベースは2311 mm、全長は3912 mm、全幅は1473 mm、全高は1448 mm、重さは737 kgだった。日本でいえば5ナンバーの小型車である。
しかし、人間とはおろかなものだ。車はもちろん、鳩までも競争の道具にしてしまう。このアングリアも、非力なエンジンながら、スチュードベーカー「譲り」の空力に助けられて、7日7晩走り続けて時速134kmという(1000cc以下のエンジンのクラスでの)世界記録を1962年に、フランス・パリ南郊にあるMontlheryサーキットでうち立てた。車の歴史も、ある意味ではおろかな、競争の歴史であった。
(上のキャロルの写真は2005年6月。東京都清瀬市の加藤自動車で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは53mm相当、F2.8, 1/125s、中のキャロルとR360の写真は2005年にトヨタ自動車博物館で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは36mm相当、F2.8, 1/5s。下の写真は1995年夏、英国ロンドンの北郊カムデンロックのフリーマーケットで。撮影機材はOlympus OM4、レンズは Tamron Zoom 28-70mm F3.5-4.5。フィルムはコダクロームKR。ISO (ASA) 64)
6-4:軽自動車メーカー、スズキの追撃。品がいい「フロンテ」で巻き返し。
スバル360を追う他の軽自動車メーカーのスズキも負けてはいなかった。マツダの4サイクルエンジンに対して、当時は排気ガス規制がとても甘かったから、排気量の割りに馬力が出て、しかもピストンが一往復するたびに爆発する、つまり4サイクルエンジンよりも倍の「滑らかさ」を発揮する2サイクルエンジンを武器に、軽自動車の一角をもぎ取ろうとした。
当時のスズキの宣伝は「2サイクル3気筒は4サイクル6気筒に匹敵」というものだった。スバル360は2サイクル2気筒、上記マツダは4サイクル4気筒だったから、スズキとしては実質、その上を行く滑らかさのエンジンを持っていることが「売り」であった。
スズキは初代「フロンテ」を1962年から売り出していた。これは スズライトバンTL型(1959年9月登場)の乗用車版「スズライト・フロンテTLA型」として登場させたものだ。エンジンは空冷2ストローク直列2気筒360cc。駆動方式は当時は珍しかったFF(前輪駆動)だった。
しかし、前輪駆動はのちに主流になるとはいえ、当時はまだ前輪駆動に必要な等速ジョイントの技術的な問題やコストの問題があり、 1967年に登場した2代目からはRR(後部エンジン、後輪駆動)に変更された。つまりスバル360と同じ方式である。またエンジンは、この2代目から、より滑らかに回る2サイクル3気筒になった。エンジンは空冷だった。
この2代目は「コークボトルライン」といわれる米国の大型自動車ではやったスタイルを採用したが、軽自動車に無理をして採用したこともあり、いかにもバランスを欠いた不格好なデザインだった。なお、この「コークボトルライン」を日本で最後に採用したのは三菱自動車の「デボネア」だったが、やはり、惨めな失敗に終わった。
この写真は1970年11月に登場した 3代目フロンテである。「スティング・レイ・ルック」と称されていたが、けれん味がなく、まっとうな形になった。RRと2サイクル3気筒は踏襲された。それゆえ、エンジンは後部にあり、エンジンを冷却するために吸気口や排気口が側面と後面に開いている。
車体の全長は299.5cm、全幅は129.5cmと当時の軽自動車の規格いっぱいだった。全高は129.5cm、ホイールベースは 201cm、車両重量は 475kgだった。幅が全幅は130cm以内と限られていたために、フェンダーミラーがとても大きく見える。もちろん、乗っている人間も異様に大きく見えた。
また、当時の軽自動車としてはエアコンはないのが当たり前だったから、(写真ではぱっくり開いている)前部のフードから空気を取込み、後部の横の窓ガラスを前方ヒンジで開けて、車内を少しでも涼しくすることが行われていた。この写真を撮った5月でも、車内は十分に熱かったのである。
ナンバープレートの色は、この車は360cc時代の車両なので小型のプレートに「白地に緑文字」(または運送事業用は「緑地に白文字」)である。現在の軽自動車のナンバープレートはずっと大きく、その色は、自家用は「黄色地に黒文字」、事業用は「黒地に黄色文字」になっている。
その後、1971年5月に、同じ2サイクル3気筒ながら水冷式になったエンジンを載せたフロンテの3代目が追加発売になった。これによってエンジンは重くなったが静かになり、また少しずつ厳しくなっていた排気ガス規制に対応できるようになった。当初は空冷車と併売していたが、のち1973年発売の4代目から水冷式だけになった。
この4代目から4ドアモデルを設定してファミリーユーズに対応したが、これはマツダ・キャロルよりも8年も遅れたことになる。
なお、1971年9月には、この3代目フロンテをベースにした、軽自動車枠のスポーツカー、「フロンテ・クーペ」を発売して、かなり売上を伸ばした。この車のデザインはジョルジェット・ジウジアーロによるスケッチをベースに、スズキが社内で作った美しいものだった。
また1970年には軽自動車で最初の4輪駆動車ジムニーがスズキから発売になり、新しい販路を拡大した。ちなみに、オーストラリアでは山地の林の中を駆け下りる自動車競技があり、ジムニーはずっと一位を確保していた。幅の狭さと軽さが身上だったのである。
その後、1975年に「安全対策・公害対策の充実」のために軽自動車の規格が改定され、車体が大きくなり、エンジンも550ccまでと拡大された。車体も全長 320cm、全幅 140cmまで拡大された。
その後、エンジン容積は1990年以後は660ccになっている。車体も全長 330cm、 全幅 140cmになった。そしてさらに1998年以後はエンジンは同じだが、前面衝突や側面衝突の安全性を増すために、全長 340cm、全幅 148cmまでとなった。これら小幅の「寸刻み」の改訂には、軽自動車メーカーと、軽自動車に市場を食い荒らされたくない既存の普通自動車メーカーの間の、政治も巻きこんだ激しい駆け引きがあった。
(写真は2015年5月。東京都千代田区秋葉原の路上で。撮影機材はOlympus OM-D E-M5)
7-1:貧しかった時代を支えたボンネットバス(いすゞBX341、1950年代)
焦土から日本が立ち上がったのを支えたの乗り物には、バスもあった。自家用車などは夢の夢だった時代に、人々の輸送をもっぱら担ったのは、このようなバスだった。
当時の日本には4つのバスのメーカーがあり、 なかでも日野自動車のバスは、もっとも鼻が高くて高貴な顔をしていたが、いすゞのバスのほうが売れていた。また、最後までボンネットバスを作っていたのもいすゞで、最終型は1970年まで作られていた。しかし、1962年からは、いすゞバス(とトラック、BXDシリーズ)は、アメリカナイズされた、なんとも品のない顔つきになってしまった。
この種のボンネットバス(車体の前部にエンジンがあり、それをボンネットでカバーしているバス)は、車体の長さの割に客を乗せる客室の長さが短くなってしまう。その後のバスがリアエンジン(エンジンが車体後部にある)やアンダーフロア(車体の下部にエンジンを詰め込んである)に変わっていったのは、そういった理由であった。
当時の日本の道のほとんどは、舗装していなかった。土ホコリを舞いあげながら走る車のエンジンにとっては、エンジンの燃焼用にエンジンのシリンダーに取り込む空気にホコリが混じるのは大問題だった。土ホコリは、つまり、細かい岩でもある。エンジンの内部をすり減らしてしまう。
もちろん、その防止のために、エアクリーナーという、空気中のホコリを取り除く濾紙(や、あるいは油の中を空気を潜らせるオイル・バスという方式の装置)がついていたが、エンジンが一回転するごとに6リットルも空気を吸い込むものだから、ホコリが多いと、すぐに目詰まりしてしまう問題が大きかった。
ところで、このいすゞのバスは全長8.3メートル、幅は2.4メートル、車体重量は5.5トンである。エンジンはディーゼル。途方もなく長いボンネットミラーを付けている。これは運輸省の「ご指導」で、現在のような、あるいは下のメルセデスのようなバックミラーが許されていなかったせいである。
ボンネットの中央前端にあるのは、ラジエターキャップだ。当時の車にとっては、オーバーヒートは日常茶飯事であり、エンジンの冷却をつかさどるラジエターの水の管理は、運転者にとって、もっとも必要で緊急度の高いものだった。エンジンフードを開けなくても、ラジエターキャップだけは、しょっちゅう開け閉めして、中の状態を見たり、水を補給したりしなければならなかったのである。
ところで、バンパー中央にある小さな穴は、セルモーターでエンジンがかからなかった場合、クランク棒を差し込んでエンジンをまわして、エンジンをかけるための穴である。 小さなエンジンならともかく、バスの大きなエンジンを手でまわすのは、大変な重労働だったにちがいない。かつて私が乗っていた1962年型の日産ブルーバードP312型や1966年型日野コンテッサ1300にも、セルモーターではエンジンがかからないときのために、このクランク穴が常備されていた。
エンジンがかかったとたんに、うまくクランクを外さないと、クランクで二の腕の骨を折ることがある。日本でも外科医の間では、運転手特有のこの骨折の患者が多くて、有名になっていた。
このバスは福山駅から鞆の浦へ行く定期観光バスに使われている。その他、レトロブームとやらで日本各地で古いボンネットバスが観光用に走っているが、そのほとんどはこれよりも後期の、つまり顔つきに品がなくなった時代のいすゞのBXD型のバスだ。
7-2:貧しかった時代の悪路走破を支えた全輪駆動のボンネットバス(いすゞTSD40、1950年代)
もっと悪い道のためには、写真に見られる全輪駆動のバスもあった。これもいすゞで、トラックにも同じ顔つきをしたものがあった。上のBX系のバスに比べて、いかつい顔つきをしている。
じつはこの顔つきは、戦後、日本にたくさん入ってきた米軍の軍用トラックの顔に似ている。カーキ色に塗られた米軍の車輌は、占領下の日本を我が物顔に走り回っていた。
このバスはそもそもトラックをベースとしたものだ。悪路や不整地用に、最低地上高が高く、腰高である。また、小回りを利かせるために、驚くほどホイールベース(前後車軸間の距離)が短い。ほとんど大型乗用車なみのホイールベースである。
このバスは高知駅から桂浜や五台山へ行く季節定期観光バスに使われている。土佐電鉄の系列会社が運航している。リーフ板バネだけのサスペンションで、ショックアブソーバーもないらしく、ホイールベースが短いことと相まって、恐ろしく乗り心地が悪い。
前のフェンダーの上に付いているオレンジ色の方向指示器は、当時にはなく、後付である。当時の方向指示器は腕木式で、運転台の三角窓の横についていて、今でも作動している。
右のバスは、上の高知の現役のバスよりも少し新しい。東京都営バスとして使われていたが退役して、都下小金井市にある「江戸東京たてもの園」にある。
これも上の高知のバスト同じ、TSD、つまり4輪駆動のバスだ。悪路用のバスだから、この写真の行く先表示板にある上野広小路行の路線で使われたものではないだろう。
この写真のバスは客を乗せて園内を走っていたが、2010年にこれも退役して、展示専用になった。
上の高知のバスとちがって、ワイパーは窓の上から吊っているタイプで、方向指示器も、いま風の点滅式フラッシャーになっている。
他方、運転席から死角になってしまう前下方を見るために、まるで海岸のシャワーのような、なんとも奇妙な形の反射鏡が着いている。子供がちょろちょろしている東京の混雑した街では必須だったのだろう。
BXやTSDといった、いすゞのこれらのボンネットバスが1970年代まで製造されていたのは、当時、日本中にあった舗装していなかった道を走るためにすぐれていたからだ。
リアエンジンバスは、どうしてもエンジンの近くから空気を取り入れるために、自分で舞いあげた土ホコリを吸い込んでしまう。つまり、日本の道が十分舗装されるまで、リアエンジンバスは出番がなかったのである。
もちろん、その防止のために、エアクリーナーという、空気中のホコリを取り除く濾紙(や、あるいは油の中を空気を潜らせるオイル・バスという方式の装置)がついていたが、エンジンが一回転するごとに6リットルも空気を吸い込むものだから、ホコリが多いと、すぐに目詰まりしてしまう問題が大きかった。
じつは、このために、旧ソ連のリアエンジンバスは、空気を天井から取り入れるという苦肉の策をとったものもあった。
このアイデアは飛行機にもあった。 1977年に初飛行した旧ソ連のアントノフ72とアントノフ74や、もっと前には1971年にドイツで作られたVFW614という双発ジェット旅客機だ(右)。
ヨーロッパでも舗装されていない滑走路が多かった当時としては、やむをえない設計だった。アントノフや飛鳥は上翼式で、その主翼にエンジンが「載っている」形だったが、このCFW614は、低翼式の主翼の上にエンジンを突っ立てる、というドイツ人らしい極端さで突っ走る設計だった。エンジンを支えるパイロンも頑丈で重いものにしなければならず、それ以上に不格好であった
外を見たい乗客にも、なんとも迷惑なエンジンだった(右下の写真)。エンジンしか見えない窓に座った客は、うるさいし、なんとも不愉快な経験をしたにちがいない。また、非常の時にも、他の飛行機と違って、機内から主翼の上に逃げ出しにくい欠点もあった。しかし、背に腹は替えられなかったのである。

なお、このVFW614は40-44人乗り。幅は22メートル、長さは21メートル。巡航速度は700km/h、航続距離1200km、最大離陸重量は20トンという中短距離旅客機だった。
なお、このように、不格好に主翼の上にエンジンを積まざるを得ない飛行機として、水上から離発着する飛行艇もある。金属のサビには大敵の海水をなるべく吸い込まないように、こうなっている。
たとえば1998年に初飛行した、ロシアの最新鋭飛行艇ベリエフBe-200がある。全長: 32 m、全幅: 33 m、航続距離: 3850 km、乗客: 64(エコノミー)、32(ビジネス)という飛行艇としては大型のものだが、大きなエンジンを二つ、主翼の上に背負っている滑稽な姿は、一度見たら忘れられないものだ。
ところで、日本でも試験的に作った「飛鳥」という飛行機が、主翼の上にエンジンを置いた不格好な形だった。この「飛鳥」は当時の運輸省主導型のSTOL(短距離離着陸)実験機で、エンジンの排気を浮揚力に使うアイデアだったが、1985年に初飛行して以来、たった一機しか作られず、わずか数年で計画が打ちきりになった。
(いすゞBXのバスは2004年に、広島県福山駅前で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは113mm相当、F3.7, 1/100s。いすゞTSDのバスは2005年に、高知駅前で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは70mm相当、F4.6, 1/500s。もうひとつのいすゞTSDのバスは2011年に、東京・小金井公園で。撮影機材はPanasonic DMC-G1。レンズは40mm相当、F4.5, 1/100s, ISO100。,ドイツVFWのジェット機は2004年8月にドイツ・ブレーメン空港で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは36mm相当、F4.0, 1/400s。VFWのジェットエンジンは。レンズは230mm相当、F4.0, 1/320s)
7-3:同じく敗戦国だったドイツの戦後を支えたメルセデスの傑作LK710 (ボンネットトラックとボンネットバス。1950年代-)
日本と同じく、第二次大戦の焦土から立ち上がったドイツ(当時は西ドイツ)では、このメルセデス(ベンツ)のトラックLK710が、復興を支えた。また、これと同じ顔をしたバスもあ った。この愛嬌のある顔をしたトラックLK710は1960年代終わりごろまで売られていた。
上のいすゞや日野のバス(トラックも同じ顔をしていた)と比べて、鼻が短いのが特徴だ。平べったい顔の日本人は(人間の顔に限らず)高い鼻に無条件に憧れ、他方、ドイツ人は鼻の長さは気にしなかったということだろうか。実際、西洋人には、鼻があまりに高すぎて、バランスを失っている顔も多い。
このLK710型のトラックやバスはとても頑丈に出来た傑作だった。また、構造も簡素で、修理もしやすかった。このため、世界各国に多数輸出されて、その後永らく活躍した。
たとえば1990年頃のアルゼンチン・ブエノスアイレスの町を走り回る、ほとんどすべてのバスや大型トラックは、この古いメルセデスだった。古くなったディーゼルエンジン特有の黒煙をまき散らしながら、狭い町中を走り回っていた。
なお、このトラックのフロントウィンドウの庇(ひさし)とそれを支える棒、ボンネット横側の翼状の飾りは、オリジナルではなく、あとから飾りのために付けられたものだ。下の写真とくらべてみてほしい。
製造から半世紀もたった今でも、数は減ったものの、南米各地や第三世界でこのメルセデスの古いトラックがたくさん走っている。
(2004年9月に、アルゼンチン・ブエノスアイレスのコロン劇場前で。コロン劇場は、アルゼンチンの黄金時代に作られた欧州にもないような豪華な劇場だ。とくに内部が豪華だ。落ちぶれてしまった現在のアルゼンチンにとっては古き良き時代の象徴になっている。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは138mm相当、F2.8, 1/125s)
7-4:そのメルセデスのボンネットトラックも、イランでは飾り立てられてしまいます
このメルセデスのトラックLK710は、なかなか愛嬌のある顔をしているし、また、それなりに端正なデザインではあるのだが、飾ることの好きな国民性が強い国では、さらに飾り立てたい欲望をかき立てるものかもしれない。
上のブエノスアイレスのトラックも後付の飾りをつけていたし、このイランのトラックも、屋根の上を始め、前や横に、あちこちに赤いワッペン風の飾りものを貼り付けている。
もっともアフガニスタンや、またフィリピンでは、車種に関係なく、さらにごてごてした飾りを付ける。このイランの程度のものは、まだかわいげがあるほうなのである。
(1977年5月、イラン南部、バンダレアッバス近くの砂漠で。撮影機材はOlympus OM1、レンズは Zuiko 100mm f2.8。フィルムはコダクロームKR)
7-5:そのメルセデス以前のトラック(アルゼンチンの裏町で)
その頑丈なメルセデスのトラックより前は、このような米国のトラックが各地で使われていた。
いまから見れば、上のメルセデスのトラックより、ずっと品がいいたたずまいをしている。エンジンの形を正直になぞったボンネット、機能をそのまま形にしたフェンダーとヘッドライト。エンジと黒の配色もいい。
じつは、日本でも、トヨタや日産で、この真似をした形の車が作られていた。知的所有権などまったく考えもしない「後進国」の自動車工業の黎明期だった。
いや、というよりは、戦争にやみくもに突入していった日本の軍需産業の要としての自動車産業にとっては、選べる唯一の道だったのだろう。
南米アルゼンチン・ブエノスアイレスの裏町にはわびしさが漂う。ほかの大都会の裏町もそれなりにわびしいものだが、ブエノスアイレスはほかのわびしさよりも深くて暗い。
それは、かつてアルゼンチンが黄金時代にあって、そのころに作られた欧州にもめったにないような豪華な町並みや大劇場が残っているまま、落ちぶれてしまったからだろう。
この写真は1990年の末に撮った。かつては美しかった欧州風の町並が続く石畳の裏通りに、すでに動かなくなった車が止まっている。向こう側のトラックは、いったい何年、いや何十年、ここに止まっているのだろう。1930年代に作られたトラックである。右後輪が外されて、代わりに木箱が支えになっている。
日本をはじめ、「先進」国では、リストアして復元する需要が多いから、まちがいなく高価で引き取られていくはずのこの車も、ここアルゼンチンでは、あまたのゴミのひとつにしかすぎないのである。
手前の1960年代の米国車も、ヘッドライトもフロントグリルも、片方のワイパーも、どこかの別の車に使われるために、持って行かれてしまったのだろう。
しかし、アルゼンチンの人々はこちらが驚くほど楽天的だ。それがせめてもの救いなのである。
(1990年12月に、アルゼンチン・ブエノスアイレスのうらさびれた裏町で。撮影機材はOlympus OM2N。レンズはコシナ28-70mm。フィルムはコダクロームKR)
7-6:上の7−1のいすゞ・BXボンネットバスの質素な運転台
このころの車の運転台は、どれも質素なものだった。今のバスと違って、計器やスイッチやパイロットランプが、なんとも簡素である。
当時の車は、トランスミッション(変速機)にシンクロメッシュがなく、ギヤの切り替えには、ダブルクラッチという特殊な操作を必要とした。いまではダブルクラッチができる人はごく少なくなってしまったが、私がいまだにマニュアルミッションの車に乗っているのは、ダブルクラッチを楽しむためでもある。
また、ハンドルは、もちろんパワーステアリングはなく、大変な腕力を必要とした。ハンドルの径が大きいのはだてではない。
エアコン?そんなものは、まったくない時代だった。フロントウィンドウの下端についているパンタグラフ型のものは、ウィンドウの上端にある蝶番(ヒンジ)を支点にして、下部を外側に押し出して開くための装置だ。
現代のWRCラリーカーが天井につけているのと同じように、ここから外の空気を車内に入れる、という単純明快な仕掛けである。運転席右前の三角窓も、外気を取り入れるためのもので、この方向(前開き)にしか開かない。
上の7-1の写真で見えるように、運転席の右足許(と対称側)には、やはり外気を取り入れるための開閉できる「蓋(ふた)」がついている。運転手の水虫予防には役立ったにちがいない。
速度計などのクラスターの上の窓際に、左右対称についているのは、フロントウィンドウの曇り止め(デフロスター)のための暖気吹き出し口だ。今の車にも、もちろんついているが、このように機能そのままで装置の存在を単純明快に示しているわけではない。
(2004年に、広島県福山駅前で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは36mm相当、F2.8, 1/60s)
7-7:上の7−2のいすゞ・TSDボンネットバスの質素な運転台
このバスの運転台も質素なものだ。速度計が120km/hまで刻んであるのはご愛敬に違いない。当時の最高速度は、エンジンもタイヤも、せいぜい60-70km/sしかもたなかったに違いない。
この車には、(悪路や急坂用の)全輪駆動と(平坦路用の)後輪駆動を切り替えるための副変速機を操作するためのレバーが床から生えている。運転手のすねの左側に立っている2本のレバーである。しかし、復元に困難があったのか、このレバーは操作できないよう、今は、金具で固定されている。
このバスは前進4段のトランスミッションで、近年のバスのものよりずっと少なかった。非力なエンジンと4段しかないトランスミッションでこのバスを操るのは、なかなかの技量を必要とした。もちろん、坂道になれば、歩くような速さになってしまった。
上のBX系バスと違って、ハンドルの軸が立っている。 トラック的である。また、ワイパーモーターも直接露出している。美観よりも機能優先なのであ る。
なお、このバスは現在使われているバス用の洗車機が使えないので、手洗いで洗っているという。
(2005年に、高知市内で。撮影機材はPanasonic DMC-FZ20。レンズは45mm相当、F2.8, 1/50s)
8-1:本田宗一郎のアイデア倒れ。消費者をモルモットにしたホンダの新鋭の車、ホンダ1300(写真はクーペ9)。
日本人が車を普通に買えるようになると同時に、それまでは見向きもされなくかった輸出先でも日本の車がようやく売れて輸出に希望が見えてきたのが1960年代の終わりだった。
上の6-1の軽自動車スバルR2が発売されたのが1969年、それとほぼ同時に発売になったのが、このホンダ1300だった。写真は当初発売されたセダンから1年遅れで発売になったクーペであ る。
デザインは米国ポンティアックの真似のフロントグリルだったが、当時としては未来から来た車のようで、また、メカニズムも画期的な車だった。ホンダが総力をあげて国際的に通用させたい車だったはずだ。
私が持っている当時のホンダ1300クーペのカタログは総カラーグラビアで45cm x 23.5cmという、私が持っている内外の自動車のカタログの中では最大のもので、28頁ある。日本国内向けのカタログだが、米国とカナダの各地を背景にこの車を配した、世界中で売りたいという当時のホンダの意気込みが伝わってくるカタログだ。
この車の「売り」は、二輪車メーカーから軽自動車メーカーへと一歩ずつ階段を登ってきたホンダとしてははじめての小型乗用車で、前輪駆動、二重空冷エンジンといった最先端の技術であった。
しかし、じつは、この車は技術的には、なんとも未熟なものだった。いや、正直に書けば、むしろ危険なものといえた。
当時、前輪駆動の乗用車としては1967年に発売されていたスバル1000があり、水平対向、アルミシリンダーの4気筒水冷エンジン、等速ジョイント、インボードブレーキ、デュアルラジエターなど、先進的な機構を備えていた名車であった。(そのスバル1000は、のちにスバル1100、やがてスバル1300になった。私はスバル1000と、1300を所有していたことがある)。
スバル1000は、 当時の世界のほかの車に負けないレベルの車だったし、のちにイタリアのアルファロメオが発売したアルファスッド(Alfasud)が真似をしたほどの車だった。なお、アルファスッドは1971年から1989年まで作られたロングセラーになった。
(しかし、アルファスッドには、使っていた鉄板の質が悪く、錆びて手に負えなくなる、という重大な欠点があった)。
そのスバル1000を追う形で開発された、このホンダ1300の操縦性は、前輪駆動車の悪い面をそのまま露呈してしまうものだった。
ハンドルを切ってもその通り曲がらない、強い「アンダーステア」、そして、その状態でアクセルペダルを放すと、突然、旋回方向に制御不能なくらいに巻き込む「タックイン」、そして、それと同時に、旋回する内側の後輪が空中に浮き上がって三輪走行になってしまう「ジャッキアップ」、といった危険な性質を持ったまま、発売されたのであった。
右の図はこのホンダ1300クーペのカタログにある、エンジンとサスペンションの図だ。とくに後輪がジャッキアップしやすい、貧弱な設計になっている。
じつは、このホンダ1300は1968年に華々しく発表されたモーターショー直後に発売されることになっていたが、実際の発売は1年近く遅れた。これは、この悪癖を手直しするための遅れだといわれている。
しかし、発売後の新車をテストしていた、自動車雑誌『カーグラフィック』(現在の『CG』)の編集長は、テスト中に車が転覆し、車内で重傷を負った。悪癖の手直しは不十分、あるいは不可能だったのである。各種の車に乗り慣れていたはずの自動車雑誌の編集長でさえ、転倒するとは思ってもいなかった場面で転倒してしまったのであろう。
その後1970年に、それまでのセダンのほかに、写真のクーペが追加された。ちなみに、この1300クーペの大型カタログには「機能的、性能的に高度で安全性にもすぐれ、さらに美的、感覚的にも極めて洗練されている」と麗々しく謳っている。ホンダに限らないが、宣伝文句というのは、そのまま受けとってはいけないものなのである。
もうひとつの技術的な「売り」であった二重空冷エンジンは、DDACと名付けられていた。ホンダの造語、Duo Dyna Air Cooling の略だという。
普通の水冷エンジンだとシリンダーの周囲に冷却水を流す「ウォータージャケット」に、強制的にファンからの空気を送り込んで冷やす仕組みで、これは、ホンダを率いてきた技術者社長・本田宗一郎氏のアイデアであった。水冷エンジンも最終的には空気で冷やすのなら、最初から空気で冷やせばいい、という発想であった。
しかし、これは、まったくのアイデア倒れだった。
エンジンを十分冷やさないと、エンジンは焼き付いてしまう、エンジンにとっては致命的なことになる。
安定して冷やすためには、アルミ製で二重になったエンジンは、水冷のものよりも、もっと重いものになってしまったうえに、冷却水の消音効果もなかった。つまり、アルミを大量に使って、コストも高く、水冷よりも重くてうるさいエンジンしかできなかったのだ。そして、このエンジンの重さが、上記の操縦性の危険さを増幅したのであった。
ホンダのほかの車と同じように、カタログ上でだけは、他車よりも馬力があった。たとえば、このホンダ1300(セダンの99)は1300ccのエンジンに4つのキャブレターをつけて115馬力(7500回転=rpmで)を出すと公称されていた。馬力の数値そのものは、当時としては1300ccエンジンの枠を超え、2000ccエンジンに迫るものだった。しかし、この馬力は、もっぱら回転数を上げて稼ぐ、いわば数字だけの馬力だった。
実際には、トルクの山がピーキーで、最大トルクは5000回転=rpmのところでしか発揮できず、低中速のトルクが痩せていて、レーシング用のオートバイのエンジンを車に載せたような、まったく使いにくいエンジンであった。さすがにホンダも、少し使いやすくするために、直後に110馬力に落として中低速トルクを少し上げたが、まだまだ、使いにくいエンジンであった。シングルキャブレターのモデル(ホンダ1300クーペ7やセダンの77)も同じように使いにくいエンジンだった。
なお、1970年にはこの”高性能”エンジンは発売をやめてしまった。あまりにも使いにくかったからである。
そしてこの車そのものも、結局、1972 年に販売中止になった。つまり、わずか3年で、寿命が尽きたのだ。
新機軸の高性能エンジン、格好がよくて速い車というカタログやセールスに釣られtて買った客は、こうしてモルモットにさせられたのである。
ところで、ホンダが客をモルモットにしたのは、ホンダ1300だけではない。
やはり華々しく売り出したホンダ最初の前輪駆動の軽自動車「ホンダN360」(左の写真。1966年の東京モーターショーで発表。1967年に販売開始)も、スタイルがよく、エンジンの公称馬力は他車よりも強く、車内は広かったが、普通の技量の運転者には危険な乗り物であった。下り坂でアクセルペダルを放すと、蛇行して操縦不能になってしまうのである。
日本中で、死者も多数、出たといわれている。当時あった「日本自動車ユーザーユニオン」という自動車の消費者団体がこれを問題にして訴訟を起こし、また当時の朝日新聞はじめ各新聞は挙げてこの消費者運動を支援する記事を掲載した。「ユーザーユニオン」は、当時米国で欠陥車問題を鋭く追及していたラルフ・ネーダーに影響を受けた、先鋭的な消費者団体であった。
しかし、結局は、ユーザーユニオンは、複数の自動車メーカーと、そして国や検察につぶされてしまった。輸出立国のための国策の策動であった。和解という”罠”に誘い込んで、恐喝罪で立件する、という筋書きであったといわれている。
【追記】そして、学問上の知識を、このようなときにこそ発揮すべきだった、各大学の自動車工学の先生たちは、裁判所が要請しても、決して、ユーザー側に立とうとはしなかった。自動車メーカーは国策企業であり、厚い国家の保護を受けていた。つまり、先生たちは、「御用学者」だったのである。
なお、肩入れしていた各新聞は、あっというまに口をぬぐって、なにごともなかったように装った。この「N360」は1967年に発売されていたが、この悪評のために1972年に販売を中止した。
ところで、ホンダ1300は3年あまりで販売中止に追い込まれてしまったが、この右の車、バモスも短命だった。
バモス・ホンダ。1970年末に、オフロード軍用車風の軽自動車だった。サイドにドアはなく、軍用車のように転落防止のバーがある。前部にスペアタイアを付けた、幌付きのオープンカーである。寸詰まりの滑稽な姿はノルウェーの小型雪上車を思わせる。
中身は、当時のホンダの軽トラック・TN360の水平横置き・空冷のエンジンや車台を流用して、作り上げたものだ。
一見、四輪駆動で、どこでも走れるような形をしているが、じつは後輪駆動で、タイヤも10インチと小さく、オフロードで走れるものではなかった。つまりデザインはこけおどしである。
もっとも、これはホンダだけが狙った商売ではなく、いすゞでも、1967年から1974年に、ユニキャブという、いかにもどこでも走れそうな、しかしじつは後輪だけの二輪駆動の普通乗用車を売っていた。
そして、ユニキャブも、このバモス・ホンダの販売も、惨憺たるものだった。バモス・ホンダの生産台数はたった2,500台で、それでもかなり売れ残ったと言われている。発表約2年後の1973年には製造を中止してしまった。
日本では、まだ米国カリフォルニア州のように、遊びのための専用車を持つほどの余裕はなかったのであろう。いわば、徒花である。
なお、1999年から、ホンダは別のバモスを売り出したが、これはなんの変哲もないキャブオーバー型の軽バンである。
(写真上は2009年5月。東京都下清瀬市の加藤自動車で。ホンダ1300クーペ。撮影機材はRicoh Caplio R1。レンズは28mm相当、F3.3, 1/164s。なお、ボンネット両側にあるミラーは、もともとの平面型のものではなくて砲弾型に替えられている。塗装が剥げて痛々しい姿だが、これからレストアされるのであろうか。もしレストアされて走れるようになるのなら、運転にはよほど注意しなければなるまい。写真中は2012年6月。愛知県のトヨタ博物館で。撮影機材はPanasonic DMC-G2。レンズは14-45mmズーム。写真下は2010年4月。加藤自動車で。撮影機材はPanasonic DMC-G1。レンズは14-45mmズーム、撮影は35mmで34mm相当、F3.8, 1/50s, ISO (ASA) 100)
9-1:トヨタに「夢」を摘み取られてしまったダイハツの乗用車、ダイハツ・コンソルテと、その前身、ダイハツ・コンパーノ。
4-1の軽三輪トラックからはじまって、4-2の小型三輪まで「成長」してきたダイハツが、つぎに狙ったのは乗用車だった。

「乗用車」は、自動車メーカーにとって、ステータスシンボルだった。
ずっとあとになってからも、トラックメーカーとして押しも押されもせぬ大メーカーだった日野自動車やいすず自動車が、乗用車生産から撤退したときに、社内の志気の衰えを隠すことができなかったほど、乗用車はメーカーにとっての憧れの製品だったのである。
とくに、三輪車メーカーとして、マツダとトップを争ってきていたダイハツとしては、なんとか先んじたい、という強い希望があったに違いない。
【追記】 ダイハツは、張り切って、イタリア人のカーデザイナー、ビニヤーレにデザインを依頼し、同社としては初代の乗用車、コンパーノ・ベルリーナ(右の写真)を作り上げた。1963年のことだ。OHVで800ccの41馬力エンジンを載せ、セダンの全長は380cm、全幅は142.5cmだった。
なおコンパーノはイタリア語で仲間、ベルリーナとは、英語ではセダンのことだ。順番としては、同年春にバン、ついでワゴンを売出し、そして11月にセダン型の乗用車を売り出した。これには、当時の通産相が陰に陽に、乗用車への新規参入を計っていたダイハツ、マツダ、ホンダに圧力をかけて妨害していたことが関係している。
デザインはイタリア風で、当時としては世界でも最先端を行くものだった。しかし、当時は国産車もフレームのないモノコック型に移行していたが、このコンパーノは、旧来の梯子型のフレームを持つ、保守的な設計で、モノコック型よりも重かった。しかし、そのために、バンや、オープンカーを作りやすかったという利点もあった。
デザインは流麗で美しく、その後、カブリオレ型の、幌のついたオープンカー、コンパーノ・スパイダーを売り出したり、OHVで800cc、出力は41馬力だったエンジンを998cc、ツインキャブで最高出力65馬力、シングルキャブで55馬力に強化するなど、商売は順調に見えていた。
しかし、コンパーノ・スパイダーの操縦性は貧弱だった。ツインキャブ型は最高時速145km/hを謳いながらも、たいへんなアンダーステアで、とても運転を楽しめるものではなかった。しかし、当時の日本車は、どれも、同じ程度に貧弱なものだった。
そして1967年に激動が襲った。ダイハツは日野自動車とともに、トヨタの傘下に入ることになり、自前の乗用車の開発から撤退させられてしまったのであった。
このため、美しいコンパーノは1969年に販売をやめ、後継の乗用車としては、トヨタ・パブリカの二代目をOEMとして売り出すことになった。
それが左の写真のダイハツ・コンソルテである。コンソルテは「伴侶」あるいは「提携」。暗喩としてトヨタとの業務「提携」を意味していたのかもしれない。
パブリカも、初代は空冷の対向二気筒を軽いボディーに載せた一応のデザインの車だったが(のちの、トヨタ・スポーツ800のベースになった。このトヨタ・スポーツ800(右下の写真)は、現在に至るまで、トヨタが作ったもっとも美しくて、いい車である)、二代目になって、水冷四気筒のエンジンを積んだ、なんともずんぐりした、デザイン不在の車に落ちぶれていた。
大型の豪華な乗用車にあこがれて、ちまちまとした物真似になってしまったのである。
なお、このトヨタスポーツの前に、トヨタは、ショーモデルとしてパブリカスポーツを1963年の自動車ショーに発表している。これは、はじめから売る気のないショー向けだけの車だった。
ダイハツは、このずんぐりした二代目をOEMで受取り、フロントエンドとリアエンドを変更し、ダイハツのエンジンを載せただけで、ダイハツ・コンソルテとして売り出さざるを得なかった。いわば、トヨタに「乗用車の夢」を摘み取られてしまったのである。このダイハツ・コンソルテは1977年まで、細々と売られていた。
さらにその後1974年に、ダイハツはシャルマンという乗用車を売り出したが、これは既に旧モデルとなっていたトヨタのE20系といわれるカローラをベースにした車だった。いわば、お古をあてがわれたのだ。ダイハツが、自分で設計した乗用車を売り出すのは、1977年、3気筒という(当時としては)ユニークなエンジンを積んだリッターカー「シャレード」まで待たなければならなかった。
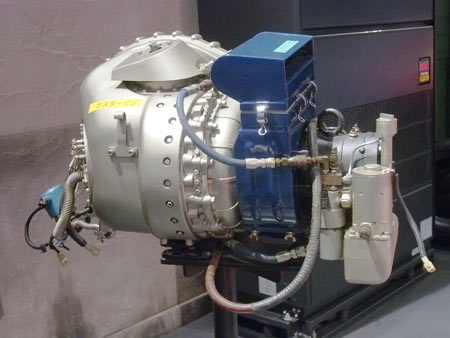
【2017年11月に追記】
上のトヨタ・スポーツ800は1965年に発表されたものだが、1977年になってトヨタはモーターショーに、このトヨタ・スポーツ800のエンジンルームにガスタービンを押し込んだスポーツカーを発表した(上の写真と右の写真)。
だが、ほかの国のガスタービン自動車と同じように、ガスタービンは出力が圧倒的に大きい割に小さいという特色があるものの、一定速でまわるのは得意な反面、自動車のように回転数も負荷も始終変わるものには向かない。
このため、このトヨタの試作車は、ガスタービンを発電だけに使って、自動車は電気モーターで駆動する仕組みにした。しかし、1977年当時はプリウスの発売よりもずっと前で、さまざまな技術的な困難を克服できなかった。
この試作車は一見、トヨタ・スポーツ800とそっくりだが、ボンネットとその切り方が違い、前部のラジエター開口部なども違う、
(写真中のダイハツ・コンソルテは2011年8月、上のコンパーノ・ベルリーナは2012年4月。ともに東京都下清瀬市の加藤自動車で。撮影機材はRicoh Caplio R1。レンズは28mm相当。写真下のトヨタ・スポーツ800は2012年6月に愛知県・トヨタ博物館で。追記のガスタービン自動車とガスタービンは2017年11月に東京・お台場のトヨタMega Web ヒストリー館の展示『自動車・動力源の変遷』で)
9-2:ホンダに「量産を打ち切られた」悲劇の車・岡村製作所の「ミカサ」
富士重工(スバル)やプリンス自動車(のちに日産プリンスになり、その後は日産に吸収された)と同じように、戦後、岡村製作所も飛行機を作っていた技術者らによって創業された。岡村製作所の場合は旧日本飛行機の技術者たちだった。
オフィス家具の製作メーカーとしてそれなりの発展をしていた岡村製作所だが、スバルやプリンスの成功を見るにつけ、飛行機は占領軍によって製造が禁止されていたが、せめて自動車を作りたかった。
こうして作り上げたのが、「ミカサ」である。1957年から1960年にかけて製造・販売された。左の写真は、東京・千代田区永田町の「オカムラ・椅子の博物館」に展示されている「ミカサ・ツーリング」である。
4人乗り、全長381cm、全幅140cm、全高136.5cm、重量610kgで、写真のように、品がいい、可愛らしい形をしていた。公称最高速度は90km/h、公称燃費は18km/litreであった。
岡村製作所は、国産車で初めてのオートマチック・トランスミッションを開発していた。このミッションは2段の機械的な変速だった。
この変速機を生かすために、「ミカサ」という自動車を作ることになったという、いわば「逆立ちした」歴史を持っている。
変速機は右の写真にあるように、現在のオートマチック車と違って、巨大なシフトレバーが生えているし、二段変速のためか、ごく小さい。今は10段変速のオートマチック車まである。
自動車を開発したときに、岡村製作所ではシトロエン2CVを購入して真似をした。2CVと同じように、当時日本では珍しかった前輪駆動方式と空冷水平対向2気筒エンジンを採用した。
この前輪駆動方式と空冷水平対向2気筒エンジンはスペース効率に優れていたが、1966年に発売したスバル1000が、ようやく前輪駆動に必要な等速ジョイントを導入して実用化したよりも、ずっと早かったために、いろいろな面で技術的に未熟なものだった。
空冷のエンジンは水平対向の2気筒。585ccで19.5馬力/4000回転のものだった。
この「ミカサ」は商用ライトバンのミカサ・サービスカー(マークIと、のちにマークII)と写真のミカサ・ツーリングの二種が製造・販売されたが、総生産台数は、サービスカーが500台余り、ツーリングが10台程度にとどまった。つまり商売としては成功しなかったのである。
だが、岡村製作所は「ミカサ」の量産体制を築こうと、生産拠点の整備や新たな生産ラインの増設を始めていた。
そこに、大きな衝撃が襲った。それはメインバンクの三菱銀行(現在の三菱東京UFJ銀行)が共通する本田技研工業がすでに二輪車の製造や販売を軌道に乗せて大きくなっていて、メインバンクが岡村製作所にオフィス家具への専念を勧めたのだった。
一方ホンダは二輪車から四輪車に乗り出して、1962年の全日本自動車ショー(今の東京モーターショー)にS360とS500が展示され、二つとも“翌春発売”と発表された。しかし、S360は断念され、S500のみが1963年10月に発売された。三菱銀行が岡村製作所に四輪車の断念を勧めた時期には、当然、ホンダからメインバンク三菱銀行へは近々、四輪車を開発するという情報が入っていたに違いない。
こうして、ミカサは1960年に生産が中止された。市場に出たのは、足かけ、わずか4年であった。こうして、日本から自動車メーカーがひとつ、消えた。
メインバンクが何を考えて、どう進めたかは詳細は分かっていない。だが、かつての飛行機技術者たちにとってみれば、ホンダやスバルやプリンスの成功は、とても悔しいものだったに違いない。
同社のトルクコンバータは生き延びて、その後、他社の自動車には採用された。1960年発表のマツダ・R360クーペと1961年発表の愛知機械工業・コニー・グッピーの軽自動車2種である。
(写真のミカサ・ツーリングとそのエンジンは2017年11月、東京・永田町の岡村製作所で撮影)
「不器量な乗り物たち」その1:生活圏編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その2:極地編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その3:深海編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その5:鉄道・路面電車編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その6:戦前・戦中編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その7:その他編はこちらへ
「不器量な乗り物たち」その8:その他編の2はこちらへ

島村英紀が撮った海底地震計の現場
島村英紀が撮った写真の目次へ
島村英紀のホームページ・本文目次へ
島村英紀の「今月の写真」へ